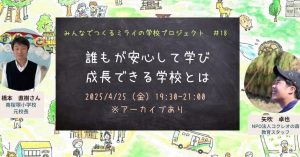
2025年4月25日に元南桜塚小学校校長の橋本直樹さんをゲストに「みんなで創るミライの学校プロジェクト」というオンラインイベントを開催しました。
みんなで創るミライの学校プロジェクトとは、コクレオの森が新しい学校づくりのための応援寄付を集めるプロジェクトとしてスタートし、今まで様々な方をゲストにお呼びして、新しい学校づくりについてイメージを深めてきました。
第18回目となる今回は、昨年度まで南桜塚小学校で元校長をされていた橋本直樹さんがゲストです。
橋本直樹さんは、今年度よりあけぼの学園に入職されており、2026年度に開校を目指して認可申請中の六瀬ほしのさと小学校(仮称)でもスタッフとして関わる予定となっています。
イベントでは、橋本直樹さんが「なぜほしのさとに関わることにしたのか」ということや教育観についてお伺いさせていただきました。
同じく六瀬ほしのさと小学校のスタッフとして関わる予定の矢吹がインタビューさせていただいたのですが、橋本直樹さんの在り方が本当に素敵でした!
橋本直樹さんは、現在あけぼの幼稚園で「なっしー」と呼ばれいるので、ここでも親しみを込めてなっしーと呼ばせていただきます。

話を聞いていて感じたのは、なっしーや豊中のインクルーシブ教育の歴史を歩んできた人たちは「インクルーシブ教育をやろう」と思ってやってきたのではなく「当たり前のことを当たり前にやろう」と思って歩んできた結果、それが結果的にインクルーシブ教育と呼ばれるものだったということです。
なっしーの話は難しい言葉は全くなく、どれもが子どもの話や、保護者との話などの具体的なエピソードです。
人として当たり前に自分を大切にしてきて、
当たり前のように周りの人を大切にしようとしてきて、障害のある人が近くにいて、その人の進路が限定されていることを知ったら、そのために声を挙げて、行動していく。
そんな当たり前のことを当たり前にやろうとする、とらわれない心を持った人たちが公立学校で誰もが共に学ぶ教育をつくってきたというエピソードはシンプルだけど、とてもパワフルだなぁと感じました。
また、著書である「こどもを分けない学校」でも書かれていた「学びの多様化学校ができることで地域との分断が進んでいくのではないか。(選択肢が増えることは良いことと前置きしつつ)」についてもなっしーがどんな考え方を持っているのか聞いてみました。
インタビュアーの僕矢吹自身も、オルタナティブスクールをやりながら年長の子がこどもの森を選ぶか、地域で友達が通う公立学校に行くかを悩んでいる場面に何回も出会ってきて、選択肢が増えるということは良いことだけではないんだなと実感していたからです。
そして、2026年度開校を目指している「六瀬ほしのさと小学校」は私立学校だけど、同じように地域との分断をつくっていくことにはならないのか?ということをなっしーに聞いてみたいと思っていました。
それに対して、なっしーが答えてくれたのは「その人にとっての故郷は一つじゃなくても良い」ということであり「地域で子育てをするという原点に立ち返る」ということでした。
その地域で子ども同士、大人同士、大人と子どもご繋がっていればどの学校に行っていたって関係ないんじゃないか。
地域に対話の文化があり、地域づくりをともに進めていること。
故郷となる地域にそんな土壌があれば、その地域のどこの学校に行っていたって関係ないんじゃないかということでした。
みなさく(南桜塚小学校)でも、教室ではなく校長室で過ごしている人がいたといいます。
「共に学ぶ」はそこにいなければならないのではなく、関係性がつながっているということが大事であり、進路(選択肢)が限定されてないことが大事だと話されていました。
なっしーの話を聞きながら、教室と学校の関係も、学校とまちの関係も一緒なんだなと感じました。
六瀬ほしのさと小学校も私立学校として特別なことをするんじゃなくて、当たり前のことを当たり前にやり、猪名川町の他の地域の学校とも溶け合っていけたら良いなと思いました。
「学校を中心としたまちづくり」のイメージがなっしーとの対話を通してさらに深まった感じがしましたし、なっしーと学校づくりができることが本当に楽しみです!

みんなで創るミライの学校プロジェクトは、今後も毎月開催予定です!
寄付者になっていただけると毎回のイベントを無料で参加していただいたり、その都度学校づくりの進捗を報告させていただいています。
ぜひ、六瀬ほしのさと小学校の学校づくりに関わってください!
(T.Y)