こどもの森ですごした人たちは今・・・
こどもの森卒業生インタビュープロジェクト第4弾は、現在、KIU インターナショナルスクールニセコ校で教師として働いているふうかさんにお話を伺いました。
*本記事は、卒業生の語りをなるべく忠実に伝えることを大切にしています。そのため、成長の途上にある姿や、まだ言葉になりきらない思いも含めて、等身大の今をそのまま受け止めながら記録しています。
ふうかさんプロフィール
- 2006年生まれ、18歳。KIU大学部学生、KIUインターナショナルスクールニセコ校国語教師(2025年7月現在)
- こどもの森学園在籍期間:中2〜中3まで(2020-2021)
- 今の自分の生き方を表す言葉:「キリストのために生きる」


学校教育の現場で働きながら、学び続ける
――今の自分の生き方を端的に表す言葉や一文を教えてください。
僕は半年ぐらい前にクリスチャンになったんです。それで、僕が今働いてる学校と卒業した学校がKIUという学校でクリスチャンスクールなんです。そこの教育を通して、聖書に出会ってクリスチャンになったので、今の身としては「キリストのために生きる」です。
――いまは、そのKIUでお仕事されているということで、どんな気持ちで、どんな日々を過ごしていますか?
KIUでは国語を教えています。卒業プロジェクトでオルタナティブスクールについて発表したり、それからバリ島のスタディツアーも企画したり、ずっと教育に興味があったので。それで、ずっと教育に関わる仕事をしたいなと思っていて。こどもの森にいた時からずっと言ってる大きな夢として、将来自分の学校を作りたいっていうのがあったんです。今は教育の現場に急にいきなり放り込まれて、日々揉まれてる感じです。教師として大してトレーニングとかも受けず、いきなり教育の現場にいて。もちろんメンターの人たちもついてくださっているので、全て自由という感じではないんですけど、それでも、色んな面で自分で設計していかないといけないということがあって。
あと学生として、大学の授業も受けてるんで、それもあってだいぶ忙しいなあと思いつつ、それまで知らなかった、実際の教師としてのリアルに触れています。それから今、学校外で外国の人とかに日本語を教えるのもちょっとしたりしてるんですけど、生徒と大人との違いっていうのを見てもすごく面白いです。生徒に関しても、小学校から高校まであるので。僕は幸いなことに、小学生と中学生と高校生のクラス3つ担当しているんです。なので、その中での違いっていうのも面白いし、更に大人も教えて、というのも面白くて。まあ忙しいながらも楽しんで過ごしております。
――なるほど。とっても忙しいですね。でも、すごく充実した感じですね。KIUの大学部でも勉強を続けてらっしゃるんですね。
そうですね。高校は3月に卒業したばっかりで。高校の時からずっと大学の授業を受けていたので、今学期で多分大学2年生分ぐらいまでの単位を取れると思うんですけど。
――こどもの森を卒業した後に、KIUに行こうと思ったのはどういう理由だったんですか?
KIUの前に、大阪にあるNICインターナショナルカレッジインジャパンっていうところに高1の時点では行ってました。そこは留学のための予備校みたいなところで、数は少ないながらも高校生も何人か在籍していました。僕は小学生の後半とか中学生ぐらいからずっと留学したいと思っていましたし、インターナショナルスクールに行って英語を学びたいというのがあったんです。
例えば、こどもの森の中学部の3年の時の自習時間は、ほとんど英語に費やしてました。数学とかは全体のグループの授業を受けてましたけど、自分ではほぼ勉強せず。こどもの森の朝のハッピータイムとか、振り返りとか、そういうのも全部英語で話してました。なので、留学したかったんですけど、海外行こうと思ったら、お金もかかるし、英語力もそこまで海外に行けるほどの能力は当時はあまりなかったので、まずNICインターナショナルカレッジインジャパンに行ったんです。もともとは、高校1年目でそこに行って、高校2年目から飛び級でアメリカの大学に行くつもりだったんです。そしたら、時間もお金も節約できるかなというのがあって。ただ、ちょうど渡航する前の学期とかに体調を崩してしまいました。親が、アメリカは医療費が高いので、向こうでまた同じように体調崩したらちょっと心配だなっていうことがありました。
――それは心配ですよね。
また円安もすごくて、生活費も高いし、学費も年間一千万ぐらいするみたいな感じで、ちょっとこれは無理だなっていう感じがあって。とりあえず日本に残る間、インターナショナルスクールに行って、英語はその方で活用できるしというので、家から一番近くて、なおかつ学費も他のインターナショナルスクールと比べたらリーズナブルなKIUに行きました。
その後も、本当は、大学はアメリカに行って、教育学とか心理学とかを学ぼうと考えてたんです。そしたら、ちょうどアメリカの大学の結果の合否が通知されてきて、まず第2志望ぐらいだったところが落ちたっていう話がメールで送られてきたんです。それで、進路相談にも乗ってもらっていたKIUの学長に相談したら、「いまニセコ校で国語を教られる人が君しかいないんだけど、ニセコに来てみませんか」という話を持ちかけられたんです。KIUで教えている国語っていうのが、結構哲学的なことが多いんです。通常の日本の学校だと、暗記とか、古典の文法とかそういうのをすると思うんですけど、そういうのはほぼ一切せず、小論文だったり、一年通していっぱいレポート書いたり、文学系の論文書いたりとか、そういう内容で、それを教えられる人がほとんどいないんです。僕は、それをやってきてたし、そういう哲学的なことを考えるのはすごく好きなんです。
日本人でなおかつクリスチャンで、それから英語と日本語両方話せて、更にその国語の内容を教えられるっていう人は、他になかなかいなくて、それで教えてくれないかっていう声がかかったんです。もとから学校を作ったり、教員をやってみたいと思っていたので。その経験がパッとできるんであれば、すごくありがたいなと思って。
こどもの森との出会い
――そもそも、こどもの森に入学するのを決めたのはなぜだったんですか?
当時、コロナが流行っていて、通っていた中学校が休校になっていました。僕が当時行ってた中学校は、マンモス校みたいなところでした。もともと行ってた小学校が逆にすごく小さくて、田舎の全校生徒20人ぐらいの規模のところで、それで地元の中学校がないから、街中の大きいところに行くみたいな感じだったんです。一年目は、部活動とか、大きなクラスも初めての経験だし、勉強は結構好きだったので、定期テストとかも、そういうのにも慣れていく中で、割と楽しんでたと思うんです。ただ、コロナが流行して、休校期間があった後に二年目が始まって。休校の間、結構好きなことをしてました。ルービックキューブにはまったり、海外に行って成功している人たちの姿をインターネットで目にしたり、自分でも何かしてみたいなと思って、メルカリで小遣い稼ぎしたりしたんです。
その後に、中学校行きだしたら、めちゃくちゃ退屈でした。割と勉強できた方なので、だいたい授業の内容わかるし。集団授業で全然面白くもないし。なんなら、これが将来どれくらい必要なのか、自分に意味があるのかも全然わからないみたいな感じで、それを親に相談しました。実はこどもの森は小2の時ぐらいにも一回見学に行ったことがあったんです。ただ家から遠くて、だいたい電車で二時間半近くかかるので、小2の時はまだ早いかな、みたいな感じで、当時は結局行かなかったんです。それで、中学2年生の時に、親にその話をして、じゃあ以前体験行ったし、ちょっと行ってみるかみたいな感じでした。それで、改めて体験に行ったら、すごく自分の好きなことを追求できそうだし、もっと意味のある学びができそうだなと思って行き出したというような感じです。
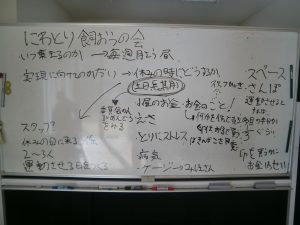

――ご両親は、こどもの森のことを知ってたんですね。
そうですね。母がもともと大学で教育学んでたりして、そういう教育には興味を持ってるみたいでした。だから小学校に入れるときも、きのくにこどもの村学園とかにも入れようかなって悩んでたことを言ってました。ただ、その時は、きのくには定員オーバーだったりして。それでもね、田舎のすごい小さい小学校を、ある意味目的を持って選びはったんやと思うんですけど。
――こどもの森に入学する時、悩んだりしたことは特になかったですか?
割とすぐパッと決めた記憶がありますね。
――こどもの森にいた時に、印象に残ってる出来事があったら教えてください。
そうですね。研修旅行がすごく楽しかった記憶はあって。僕の時は二年ともコロナで海外には行けなかったので。その分、子どもが研修旅行の企画に関われる割合がすごく大きかったです。そういう経験が、スタディツアーを企画したりするのには繋がってたかな?学校外とかでも、旅行を自分で企画して、友達連れて休みの日に何かキャンプ行ったり、スキー旅行行ったり。そういうのが割と好きだったので。あとは、卒業プロジェクトは、どういう方向性でいくか、すごく悩んで。途中ぐらいから、オルタナティブスクールをいろいろ見に行って、インタビューしたり、学校見学して気づいたことをプレゼンにまとめたみたいな感じでした。卒業プロジェクトで、最初に見に行きたかった場所が、グリーンスクールだったので、それはその後のスタディツアーに直接繋がっていますね。あとは英語かな。英語は一年ですごい伸びた。やっぱり自分で、自由度を持って自分の学びを設計できたおかげで、急激に一年ですごい英語力が伸びたんです。結果として、こういう場所で働けるようになりました。
――英語はどんなふうに学習したんですか?
初めは、まずきっかけとして、当初行きたかったISAKっていうインターナショナルスクールのウィンタースクールがあって、それに参加したんです。そこで自分の英語力の低さを痛感させられました。周りもほぼハーフとか帰国子女とか、ペラペラな人ばっかりで、もう全然先生が何言ってるかもわからなくて。そこから帰ってから、まあ本気で勉強しなあかんなと思いました。初めはもうできるだけ、全ての生活を英語に変えようと思いました。家族に英語で話しかけてみたり、こどもの森でも、できるだけスタッフとか友達とかにも英語で話そうとしたんですけど、なんせ相手は伝わらないし。兄弟なんかにはちょっと気持ち悪いからやめろ、とか言われて(笑)
人とコミュニケーション取らない時でも、こどもの森の学習の振り返りとか、何でもそういうものを全部英語にしました。スマホの設定を全部英語に変えたり、あとは、もうできるだけ英語に触れる時間を増やしました。駅や電車で、ずっとTEDトーク聞いたり。自習時間の時は、英語でちょっとエッセイ書いてみたり、帰ったら英語のyoutube見てみたいなこと、そんな感じを一年続けたら、なんか伸びてました。

――いろんなツールを駆使して、独力で英語学習をしてたんですね。まさに主体的な学びだと思います。少し話は戻るんですけど、研修旅行はどこだったんですか?
研修旅行は徳島に行きました。神山高専がちょうどできるか、できてから間もないときくらいだったと思います。その話を聞いたり、リサイクルをしてる自治体の話を聞いたりしました。あと色んな国の人がその地域に来て、山にアート作品を置いていくっていう、そういう取り組みをしているところがあったりしました。あと、蔵にみえるところが実はすごいサーバーで、中に色々なインターネットの機器が入ってたり。めっちゃ田舎に見えるんだけど、実は色々な会社のサテライトオフィスがすごくあって、その話を聞きに行ったりしたかな。
――みんなで行く場所を決めたんですか?
最初は生徒からいろんな案を出し合いました。僕はやっぱり当時から教育に関心があったので、長野の教育を見に行きたいとか言ったりしたんですけど。沖縄とか他にも案はあったんですけど、研修旅行は基本、向こうの現地の学校との交流とかもあるので、そういうコネクションがあったりするところということで、ある程度スタッフが案出したり絞ったりして、結果的に徳島になったと思います。
――そうやって研修旅行も企画していったんですね。では、これまでの自分にとって、生き方や進路を決める転機だと思うような出来事はありますか?
うーん、まあ二つぐらいかな。一つ目は、こどもの森に入った時で。やっぱりコロナでだいぶ自分の人生変わった感じがあります。コロナがなかったら、多分そのまま普通に高校進学して大学も行って、まあ割と普通の人生を歩んでたんじゃないかなと思うんです。コロナでちょっと自分の興味を見つめ直す時間ができたおかげで、こどもの森に行って、英語と教育をとことん追求して、今こういうところにいるので、それは大きいのかなと思います。あともう一つは、クリスチャンになったことは多分一番大きいかな。中学生ぐらいの時から、ずっと考えることは好きで、いろいろ世界のあり方とか、人間の生きる意味とか、そういう哲学的なことを考えるのすごく好きだったんですけど、クリスチャンになって、聖書を学び出してから、だいぶその思考のプロセスとか全部ガラッと変わりました。生きる意味っていうのがやっぱり一番違うかなっていうのは思いますね。
コンフォートゾーンから飛び出すこと
――こどもの森への入学がひとつの転機になったということですが、改めて、こどもの森での経験が自分にどのような影響を与えたと思いますか?すでにある程度お話しいただいたとは思うのですが、もし言っていないことがあれば。
話してないことで今あると思うのは、当時の中学部のスタッフの”れなさん”っていう人が、ワールドリエンテーションの時だったか、何かの時に、自分のコンフォートゾーンから飛び出して何かをするっていうことを言ってたのが、ずっと印象に残ってます。なので、スタディツアーを企画したのもそれがあったんですが、それから、能登の地震があった時に、震災の一ヶ月後ぐらいからボランティアに行ったんです。今まで5回ぐらい行きました。危険でどうなるかわからないし、しかも学校が普通にある日だったんです。学校終わって、金曜日の夜に出て土日活動して戻ってくるみたいな感じで、行くのかどうかもその時も悩んだりとかしました。そういうチャレンジをした時は、やっぱり自分のコンフォートゾーンから出ないとなっていうのがあったんです。今の場所(ニセコ)に来るのを決めた時も、そうですね。はじめは、話をもらった時にプレッシャーや期待だったり、自分に本当にそんなことができるのか、という気持ちになったり、一人暮らしをして、環境も変わって急に教師として行くなんて、とか思ったんですけど、やっぱりそのコンフォートゾーンから抜け出すっていうのは、常に自分に影響を与えてきたなっていうのはあります。
あと、当時感じていたこととしては、そして今でも思っていることは、こどもの森が教育の最適解では全然ないし、こどもの森が拾えていないところは沢山あると思っています。僕の同級生は、いま立命館アジア太平洋大学(APU)に行ってるんですが、彼もすごく芯があって、中学生になる時に、自分でこどもの森を見つけてきて、自分の親にこういうところに行きたいっていうふうに説得して来た子なんです。まあ自分も親に相談して、決めたのは自分ですけど、それでも流れてきてる感はあって。その同級生は常に芯があって、農業もずっとしてて、高校は農業高校行ったんです。プロジェクトで、自転車で四国一周して、クラウドファンディングして、何十万とか達成したりして。僕も英語とか教育とか、割と芯がある方だったかなと思うんですが。
卒業プロジェクトでいろんな学校見に行ったりして、最後に思ったのは、結局教育にできることはそんなにはなくて、結局は、その子に一番合った教育を見つけられればベストなんだけど、それが難しいよねっていう話で。それは結構思ってましたね。

――実際に教育に携わっていて、そのように感じたりすることもありますか?
今はまだ生徒数がそんな多くなくて、小1から高1まで多分30人いないくらいです。僕が持っているクラスも最大で5人とかなので、まだ生徒のニーズに応じてアジャストできたりはするんです。僕は、こどもの森の教育観から影響を多分受けていると思うんですが、それはKIUの持ってる哲学と違ったりするので、その中でどこまで子どものニーズに応えるのがその子にとってのベストなのかっていうのがあります。自分が教えるべきだと思うことと、子どものニーズとのギャップとか。子どものしたいことを全てやらせてあげるのは、僕はあまり正解だと思わないので、そのバランスがすごく難しいなっていうのはあります。ちょっと間違えると、本当に学級が保てなくなって、あまり良いクラスになってなかった時期もあったりしたので、その難しさは感じてはいます。
――教育の現場で難しさを感じているなかで、いま何を大事にしていますか?
繰り返しになってはしまうんですが、クリスチャンになってからは、神様がどういう風に生きてほしいのかっていうのが一番で、やっぱり自分にどういう計画があって、どのように生きるべきかということですね。今一番自分が思うのは、自分がしたいことと、自分が生きるべき生き方というのはやっぱり違うということなんです。自分に与えられている能力とか、自分が向いていることとか、それによって導き出されるというか。やるべきことっていうのと、自分がしたいことっていうのは、常にリンクしてないので。興味っていうのは、ある程度、自分の進路を作っていく、重要なファクターの一つだと思うんですけど、それだけじゃなくて、自分はこういうことに向いてて、社会にこういう必要があるから、自分は人のためにこういうことをしようとか。社会に困っている人がいたら、自分が100パーセントしたいことってわけでなかったとしても、自分の今持っている能力と環境で、できることはこれだなって考えていきたいと思っていますね。まあ、興味ってすぐ変わるので。僕も割と自分の好きなこととか、やりたいことは、常に変化している感じはあるんです。ただ、自分の向いていることとか得意なことって、なかなか変わったりしないのかなと思うので、何をやるにしても、どんな方面に行っても、自分の能力を必要としている人のために何ができるかっていうのを考えていきたいなと思っています。
――いま言っていただいたことと関係するとは思いますが、これからどんな風に自分の人生をデザインしていきたいですか?
やっぱり今言ったことが一番大きいのかな。マタイの福音書に「隣人を自分のように愛しなさい」というのがあるので。愛っていうのは感情だけじゃなくて、行動も含めて愛だと思うので。他者をどうやって愛せるか、その愛に基づいて行動できる、そういう仕方で人生のデザインをしていきたいと思っています。
――このたびは、社会人として、学生として、忙しい中で、お時間割いていただきありがとうございました。私としても、学びの多いインタビューでした。
インタビューを終えて・・・
私は小学部に通っている子どもの保護者ですが、もともと自分自身が不登校で、その経験から当事者としてオルタナティブ教育に関心を寄せていました。今回、スタッフの方から、ふうかさんが、 中学部の卒業プロジェクトでオルタナティブ教育についての発表をしたり、高校時代に、グリーンスクールやエンパシースクールを取材したバリ島スタディツアーを企画したということを聞いて、ぜひお話伺いたいなと思い、インタビュアーとして名乗り出ました。
中学部の卒業プロジェクトでオルタナティブ教育についての発表をしたり、高校時代に、グリーンスクールやエンパシースクールを取材したバリ島スタディツアーを企画したということを聞いて、ぜひお話伺いたいなと思い、インタビュアーとして名乗り出ました。
ふうかさんは数ヶ月前に高校卒業したとは思えないほど落ち着いていて、非常に聡明な方でした。ふうかさんは自律的に考えて、道を切り拓いていけるというだけでなく、自分自身を他者や社会との関係性のうちに捉えることができる視野の広さを持っています。このように芯の通った人だからこそ、こどもの森の中学部での自由度の高い学びや対話の時間がフィットしたのだと思います。ふうかさん、素敵なお話を本当にありがとうございました! (S.H)
追記:ふうかさんが、もりラボで企画したバリ島スタディツアーの報告会のブログはこちらです。ふうかさんの卒業プロジェクト「オルタナティブ教育」の発表の動画も見られます!